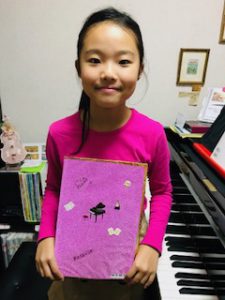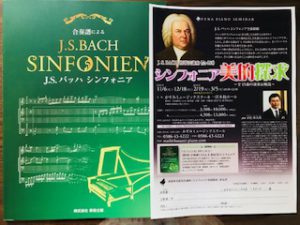中村紘子先生に演奏ささげる 牛田さん決意
世界中から若き才能が集う第十回浜松国際ピアノコンクール(浜コン)。開幕を二日後に控えた六日、出場登録のため会場のアクトシティ浜松(浜松市中区)を訪れたピアニストの牛田智大(ともはる)くん(19)=名古屋市=は、“先生”への思いをあらためてかみしめていた。 日本人ピアニストで史上最年少の十二歳でCDデビューを果たし、メディアでもてはやされた「天才少年」。その牛田くんを「ピアニストの道」へ導いてくれたのが「先生」こと、故・中村紘子先生だった。 世界的なコンクールへと育てた中村先生。牛田くんは11歳と12歳の時、中村先生らが若手ピアニストを短期レッスンする「浜松国際ピアノアカデミー」に参加。12歳の時はレッスン生による模擬コンクールで1位になった。
そんな天才に中村先生は厳しい言葉をかけ続けた。「才能はあるけど実力はない」「タレントじゃなく、一流のピアニストになれ」。派手な自己アピールを嫌い、具体的な演奏技術はもちろん、ピアニストとしての心構えや、環境のあり方を牛田くんに教えてくれた。「(先生と出会った)浜松からピアニスト人生が始まった」という。 子ども時代からリサイタルに協奏曲にと演奏活動を行い、ファンも多い牛田くんにとって、予選会場となるアクトの中ホールは牛田くんにとって特別だ。一昨年二月、アカデミー設立二十周年を記念したコンサートで演奏したが、体調不良でまともに弾くことができなかった。客席にいた先生の前での「悔いが残る演奏」。 中村先生はその年の七月、病に倒れ、帰らぬ人となった。「あの演奏が最後になってしまったんです」 今回の浜コンで、牛田くんは予備審査(応募者約450名のDVD審査→95名を選抜なので、約2割強)を通過し、1次でプロコのピアノ・ソナタを、2次でラフマニノフのピアノ・ソナタを弾くらしい。どちらもあのコンサートで満足に奏でられなかった曲だ。 |
|
 先日もUPしましたが、写真は2012年2月、中村紘子先生(左)と並ぶ、模擬コンクール1位に輝いた牛田智大くん(右)とラナ・ベアトリスさん。浜松市中区のアクトシティ浜松にて。
先日もUPしましたが、写真は2012年2月、中村紘子先生(左)と並ぶ、模擬コンクール1位に輝いた牛田智大くん(右)とラナ・ベアトリスさん。浜松市中区のアクトシティ浜松にて。