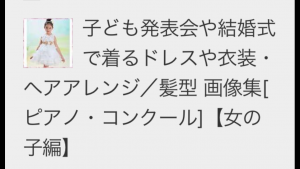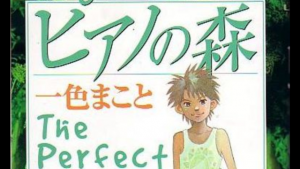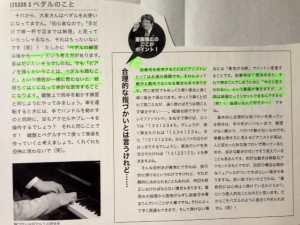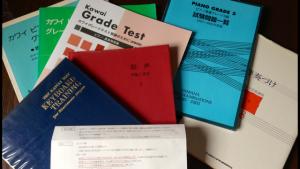きらめき音楽祭にご参加希望の人が多く、皆さんのチャレンジ精神に拍手を送りたいと思います。
人それぞれ、エチュードレベルで挑戦されるコースが決まります。
では、どんな人がいらっしゃるかご紹介いたしましょう。
①課題曲例をストレートに選ばれる人、②課題曲例は難しいからもう少し簡単な曲でバッチリ弾いた方がカッコイイと思われる人、③課題曲例より(自分のレベルより)背伸びして難しい曲に挑戦したい人、④8月は簡単な曲にして、もし通過出来たら、11月に派手な曲にしたい人、⑤初めから目立つ曲を選び、11月も同じ曲で磨きをかけて再挑戦し、大きなトロフィーを狙う人、⑥11月は他のコンクールの課題曲を弾いて講評を頂きたいので、8月は無難に通過できる曲を選ぶ人、⑦簡単で楽しく弾ける曲を選んだ人、⑧度肝を抜くくらい派手なパフォーマンスで弾き、聴衆を驚かせようとしている人・・・考え方は十人十色です。
先日ご入会頂いた人ですぐに曲が決まった人もいらっしゃいますが、曲がまだハッキリ決まっていない人、曲を迷われている人、先生からまだ参加のOKが出ていない人もみえますが、5月までなら間に合います。きっと楽しいstageになると思いますので、キラキラ輝く為に頑張りましょう!