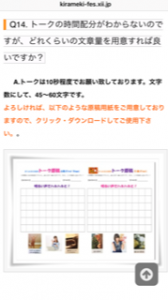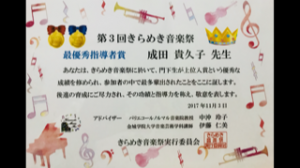きらめき音楽祭Finalが終わりました。
皆さん、よく頑張りましたね。
審査員の先生からは「クオリティが高い演奏ばかりで驚きました!」
「1~2つ星は可愛らしい感じでしたが、3つ星から急にレベルが高くなったように感じました。」
「とても上手い子が何人もいて、本当にレベルが高い演奏でした。」
というようなお言葉を頂きました。
確かに3つ星以上は上位3賞(金銀銅)は電子ピアノではなかなかGET出来ませんね。
悔しい思いをして涙した人もいらしたようですが、良い勉強になり、改善点を見つけることが出来たと思います。前を向き、すぐ次の目標に切り替えて下さい。
保護者の皆さんからご感想のメールを頂き、有難うございます。その中で、印象に残ったものは・・・「審査員の先生のコメント用紙を見て、うちの子の演奏であまりにも審査の先生に見透かされたようで驚き、感動し、涙が出てきました。」と仰った保護者の方もいらっしゃいました。演奏はその子の性格やピアノを学ぶ姿勢がバレてしまいますよね。
「私、こんなに頑張ったのに何故トロフィーがないの?悔しい~!」「間違えずにちゃんと弾いたのに、どうして?」という人もいらしたようで、あとで努力の度合いの違いを思い知ったようです。井の中の蛙ではダメですね。自分で良い演奏をしたと思っていても、それが舞台で気持ち良く弾けただけであって、左手の弾き方を注意するのを忘れた~!ってことはありませんか?または音が抜けちゃった~!とか、どうでしょう?
頑張っている子は本番が近づいて来たら、朝、学校に行く前に練習し、学校から帰宅後すぐに練習し、夕食後にまた練習されていたようですね。
また、レッスンの様子をIC録音やスマホで撮って、家で何度も見たり聴いたりして研究されている保護者の人も数人いらっしゃいました。
本番当日はホワイエで自分の練習風景の動画をアイパッドで見聴きしながら指を動かし、イヤホンで聴いている人も数人見かけました。
レベルが上になれば、コースの星もトントン拍子で上がれなくなるのは当然です。レッスンの練習曲が難しくなり、曲も長くなりますからね。音楽の世界は奥が深く、甘くありませんね。だからこそ、根性を出して、努力することを学べるのです。
毎回、レッスンの時、学ぶ姿勢が出来ている子とそうでない子の差が結果にも表れます。やはり、積み重ねが大事ですね。何でも甘く見ちゃダメ!ってことですね。
きらめき音楽祭はご参加の年齢制限もないので、ずっと楽しく学ぶことが出来ます。
是非、次もチャレンジされ、一緒に成長したいと思います。
引き続き、保護者の皆さんのサポートを宜しくお願い致します。
【追伸】
デュオのFinalは金賞、銀賞、奨励賞のいずれかです。上位の賞しかないので、確率が高いかも?
金・銀の響きがイイですね。
来年、デュオにチャレンジされたい子は考えておいてください。宜しくね!
 きらめきを終えて、打鍵力強化、指の形の矯正、姿勢などを考えて、中級レベル頃からプレインベンションを加えます。
きらめきを終えて、打鍵力強化、指の形の矯正、姿勢などを考えて、中級レベル頃からプレインベンションを加えます。